祖父から譲り受けた江戸時代後期の蕎麦猪口(花菖蒲文)を、日常で使っています。
もともと蕎麦猪口は「生活雑器」。飾るだけでなく、使ってこそ価値がある器です。
ただし、使うとなると心配なのが“割れ”。
もし落としてヒビが入ったら? そんなとき頼りになるのが「金継ぎ」です。
金継ぎとは?
金継ぎ(きんつぎ)は、割れた器を漆と金粉で修復する日本の伝統技法。
単なる修理ではなく、欠けやヒビを“景色”として活かす美しい補修方法です。
しかし、職人に依頼すると工程が多く、費用もかかります。
場合によっては蕎麦猪口の数倍の金額になることも。
高級な骨董品ならともかく、手頃な蕎麦猪口だと迷ってしまいますよね。
過去ブログで書いた、”機械式時計の本体価格よりも定期的なオーバーホールの費用の方が高い”現象です。
自分でできる「金継ぎセット」が人気
最近では、初心者でも使える「金継ぎセット」が販売されています。
漆や金粉の代わりに、強力な接着剤とアクリル絵具(ゴールド)を使う簡易金継ぎも登場。
動画やSNSで手順を紹介している方も多く、「自分で直してみる」時代になっています。
食品に使う器の場合は、食品安全認証付きのボンドや耐熱性アクリル絵具を選ぶのが安心です。
本格的な金継ぎの工程
伝統的な金継ぎでは、漆を塗っては乾かし、磨いてを何度も繰り返します。
乾燥だけでも数日単位、完成まで1か月以上かかることも。
ヒビ割れはV字に削って漆を埋め、欠けはパテで整形するなど、まさに職人技です。
使いながら楽しむ蕎麦猪口
以前は“鑑賞専用”としていた江戸時代初期の露草文の蕎麦猪口も、これからは使ってあげようと思います。
熱々のエスプレッソを注ぐ“濃いめのアイスラテ”にも耐えてくれます。
器としての実用性も高く、まさに「使って育てる」楽しみがあります。
割れたら終わりではなく、“景色”になる
金継ぎの魅力は、壊れた器を美しく蘇らせること。
補修の跡が金色のアクセントとなり、世界にひとつだけの表情を生み出します。
何より、“直して使う”という行為に、使い手の想いが宿ります。
まとめ
蕎麦猪口は「骨董の入り口」とも言われる親しみやすい器。
そして金継ぎは、壊れた器を蘇らせる日本の知恵です。
割れたら終わりではありません。
飾るだけでなく、使いながら愛でるのもまた、蕎麦猪口の楽しみ方です。
さて、あなたは飾る派?それとも使う派?



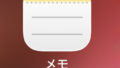
コメント