“人喰いバクテリア”による右足切断後の半年間の入院生活で、ほぼ毎日3回、食事のたびにいただいたほうじ茶。香ばしい香りと飲みやすさが、病室での小さな救いになりました。
最近、ほうじ茶をお家カフェで飲んでいます。
そんなほうじ茶ですが、あまり知らなかったので深掘りしてみましたので共有させていただきます。
病院でほうじ茶が提供される理由
- カフェインが少ない:100mlあたり約20mgと控えめで、体調が優れない人にも安心。
- リラックス効果:ピラジンなどの香り成分がストレスを和らげ、病院の不安を軽くする効果が期待される。
- 渋み・苦味が少ない:焙煎工程でクセが減り、年配の方や嗜好の合わない人にも飲みやすい。
- 大量に作れて管理しやすい:煮出しで一度に作れるため、病院側の運用上も扱いやすい。
- コストパフォーマンス:高級茶やペットボトル飲料に比べ経済的で、病院食にも向く。
ほうじ茶とは
「焙じ茶(ほうじちゃ)」は、煎茶や番茶などの茶葉を強火で焙煎し、褐色になるまで火を通したお茶です。
青臭さや渋みが飛び、香ばしい香りが際立つため、食後にすっきりと飲めるのが特徴。
近年はほうじ茶ラテやスイーツなどの流行で若い世代にも人気が広がっています。
歴史と誕生秘話
ほうじ茶は比較的歴史が浅く、大正末期〜昭和初期に京都の茶商が売れ残りの茶葉を有効活用する中で広まったとされています。
一説には大学の学生が鍋で茶葉を焦がしてしまったことが発端という話もありますが、森永製菓が大正14年にほうじ茶を発売していた記録もあり、起源には諸説あるようです。
原料と種類
主に番茶が原料として使われることが多く、遅い時期に摘んだ葉(お番茶)は香ばしさが引き立つため、ほうじ茶向きとされます。代表的な種類は以下の通り:
- ほうじ番茶
- ほうじ煎茶
- 京番茶
- 加賀棒茶(茎を焙じたもの)
- 雁ケ音ほうじ茶
- 三年番茶
胃に優しいお茶
焙煎によって苦味や渋味が抑えられ、カテキンも控えめになるため、子どもや妊婦さん、胃腸が弱っている方でも比較的飲みやすいお茶です。
刺激が少ない点が病院で評価されています。
香りの正体
「焙じる」ことで茶葉中の青臭さや渋みが飛び、代わりにピラジンなどの香ばしい香り成分が立ちます。温かいほうじ茶はその香りがより立ち、飲むだけで気持ちが落ち着きます。


私の鉄瓶とほうじ茶の楽しみ
自宅では愛用の鉄瓶でほうじ茶を淹れています。注いだ瞬間の芳ばしい香りが心地よい時間を作ってくれます。
鉄瓶は注ぎ終わったら余熱で乾燥させますが、鉄瓶の内側に残った香りも格別です。
使っている煎茶鉄瓶は内側に茶漉しがあり、ステンレス製の後付け茶漉しより穴が大きめなので、細かい茶葉が湯呑みに少し入ってしまう点が欠点(私は好み)なんですが、逆に”茶柱が立つ可能性が高い”ので、楽しみにしています。
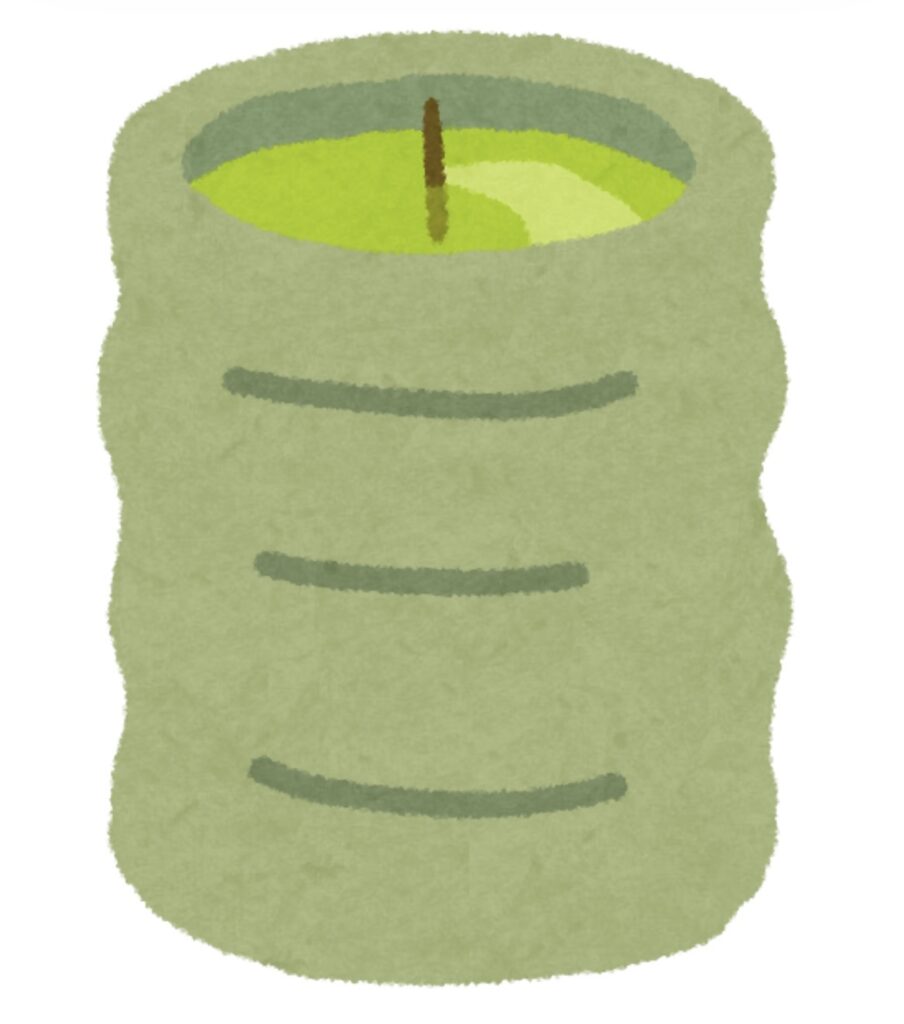
最近、茶柱が立ったことがありますか?




コメント